4月5月は教員採用試験出願時期真っ最中ではないでしょうか。6月から一次試験も始まり勉強している人も多いかと思います。

勉強したいけど、講師として働きながらだから時間がないよ…それに何を重点に勉強しよう…

教員採用試験で重要視されるのは面接!面接の練習を重点的にしよう!
僕は面接が得意だったので面接を武器に採用試験を一発合格できたよ。
1. 最初の「失礼します。」で勝負は決まる。

人の第一印象は最初の3秒で決まると言われています。
もちろんそれが全てとは言いませんが第一印象って大切ですよね。
面接で最初に話す言葉、それは自己紹介でも自分の名前でもなく、
「失礼します。」です。
そこで面接官に
「この子は元気がいいな。」とか
「明るそうだな」とか
「(教育業界の厳しい環境でも)やっていけそうだな」とか
思わせたら
勝ち
な訳です。
最初だから緊張してるかもしれませんが、
ここに全てのパワーを使って大きな声で元気よく、「失礼します!」を言いましょう。

いや、僕の売りは落ち着いているところだから無理して大きい声出すのは…

もちろん自分の売りを出すことは大切。でも面接では偽ってでも「元気」な姿勢でいくことをお勧めします。理由は…
「落ち着いている」と「元気がない」は判断がつきにくいから。
教育という現場では子どもに負けない元気さ(パワフルさ)が必要だから。
そして最初に声を張っておくことで緊張が解ける、その声がスタンダードになるという利点もあります。
緊張して入って、最初に声が出ずにそこから調子が出ず…ってことがなくなります。
しかも難しいことを考える必要は一切なし。
ドアをノックして深呼吸して元気に「失礼します!」というだけ。
これだけでこの後の展開が一気に楽になります。
2. 答えの軸を用意しておく
「答えの軸」というのはつまり「自分の軸」です。
「自分という人間(長所や短所)」「教育観」などです。
軸が決まっていることでそこに向けて回答をしていくと1本筋の通った面接の回答にすることができます。また、ゴールが定まっていることで回答も思いつきやすいです。
例えばどんなものかというと、僕の場合(当時)は
長所:積極性と明るいところ
教育観:生徒を中心に、生徒と共に
です。
まずこの「自分」というところをしっかり固めておくことが大切になってきます。
どうこれが響いてくるかはこの後紹介していきます。
3. 答えられなきゃいけない質問は必ず用意(練習)しておく
全ての質問の答えを用意するのは不可能ですが、
「これは今考えちゃダメだろ…」っていう質問の答えは必ず用意しておきましょう。
具体的には
「教員になりたい理由」
「どうして小学校(中学校・高校)なのか」
「どうしてその自治体なのか」
「自分の長所、短所、自己PR」
少なくともこれらは必ず用意しておきましょう。
僕の希望していた自治体ではほぼ必ず1分間の自己PRが出ると言われていたので死ぬほど練習しました。覚えている限りで紹介させてもらいます。
「私の長所は2つあります。1つ目は積極性です。私は大学で1年間の小学校でのボランティア、半年の中学校でのボランティア、その他にも多くのプログラムに積極的に取り組んできました。これらの経験で大学のキャンパスでは決して学ぶことができない多くのことを学ぶことができました。教員になっても積極性を持ち、何事にもどんどんチャレンジして、成長していくことができます。2つ目は明るさです。私の名前の陽の字は「太陽のように明るく生きる」という意味を込めてつけられました。名前のようにどんなに辛いことがあっても明るく、楽しく、毎日を生活することができます。この2点を学校現場に入っても生かし、生徒とともに、楽しみ、一緒に成長していく教員に私はなります。」
全て覚えているわけではありませんが、こんな感じで1分間の自己PRを作りました。
ちなみに、
面接を練習する順番として
まずはこのように自分の長所や短所、自己PRを作ることをおすすめします。
自分を分析し、知り、言葉(文字)にすることで先ほど書いた「答えの軸」も決まってきます。
4. 答えをパターン化する。
個人面接でも集団面接でもやはり質問の答えの質は大切です。

用意した質問にはなんとか返せるんだけど、用意してない質問の返しにパニクっちゃって…

それは1つのコツと練習で解決できるよ
面接って用意されてない質問や、答えにくい質問がきたらパニックになって、何かしゃべろうとして話し始めると訳わかんないこと話し始めて…ってことありますよね。
僕は以下の考え方で面接の答えをパターン化しました。
自分の答え(簡潔に)
→そう考える根拠や理由(経験談などを絡めるとGOOD)
→Topicを学校や教育関係、未来の自分に結びつける
少し文章にすると難しいので質問例をもとに解説していきます。
質問:中高の部活について。部活を通して何を学びましたか。
答え:はい、私は中学、高校とサッカー部に所属していましたが、そこで仲間と一つの目標に向かって努力することの素晴らしさを学びました。(自分の答え)
しんどい練習も多く、仲間と衝突することもありましたが、それらを乗り越えることで自分自身が強くなり、仲間との絆を深くすることができました。(理由)
この経験を生かし、教員になってもどんなことでも他の教職員の方や生徒と協力し、乗り越えていくことができます。(結び付け)
このような3段構成で答えることを意識しました。
最初は少し難しくても練習していったらできるようになるし、自分の型を決めると話が右往左往しなくなります。
ここに先ほどの答えの軸を組み合わせていくと、より強いメッセージを込めた回答にすることができます。
もう1つ例を紹介します。
質問:休日はどのようにして過ごしていますか。
答え:はい、休日は趣味のボルタリングを最近しています。(自分の答え)
身体を動かすことが好きで、友人と最近始めました。その他にも興味があるものに積極的にチャレンジしています。(経験談)
教師として働いても、休み時間も生徒と一緒に遊び、持ち前の積極性を生かして色んなことにチャレンジしていき子どもと共に成長していきます。(結び付け)
このように「積極性」「明るさ」「生徒中心に」「生徒とともに」という
自分の長所や教育観を何度も引き出しから出して答えに結びつけることによって、自分の信念を伝え、自分という人をアピールできるのです。
5. 周りとの差別化をする
これは面接官のタイプにもよるし、うまくいかないと大コケするので諸刃の剣的なところはありますが…一応紹介しておきます。
面接ではいわゆる「普通の人」では差がつきません。
答えの質や、立ち振る舞いで普通のことをしていては周りと一緒です。
サッポロビールの面接で面接中終始何も話さず最後に一言だけ
「男は黙ってサッポロビール!」(昔のサッポロビールのCMのセリフ)
とだけ言って採用になった、という話は有名ですね。

なので「どこで」「どんなふうに」周りと差をつけるのかを考えて面接練習をすることは大切です。
僕の場合は「誰にも負けない元気さ」と大量の練習による「答えの質」で差別化をはかりました。
あとは本命の自治体の筆記と面接が緊張によりあまりにも出来が悪く、一発逆転を狙って模擬授業で「英語の歌を歌いながら入室し、決めポーズをして挨拶をする」という博打にも出ました笑
(その自治体だけ残念ながら落ちてしまいましたが…笑
あれでだいぶ点数はまくれたと思ってます笑)
自分が何を売りにし、何で周りと差をつけるか、自分の武器を持って面接には臨みましょう。
最後に
面接官が「あなた」という人を判断できるのは
見た目(雰囲気+所作)
質問の答え(+答え方)
しかありません。
たった10分、15分で人を完璧に判断することはできません。
言い方は悪くなりますが少し背伸びして自分を見せてもバレないのです。
一番大事なのは、自信を持って、
「学校現場に行ってもこの人は大丈夫だ!」と思わせることです。
そして自信を作るものは何よりも練習です。練習量です。
ぜひこれらの方法を参考に練習してみてください。
採用試験を受ける皆さんを応援しています。
読んでくださりありがとうございました。
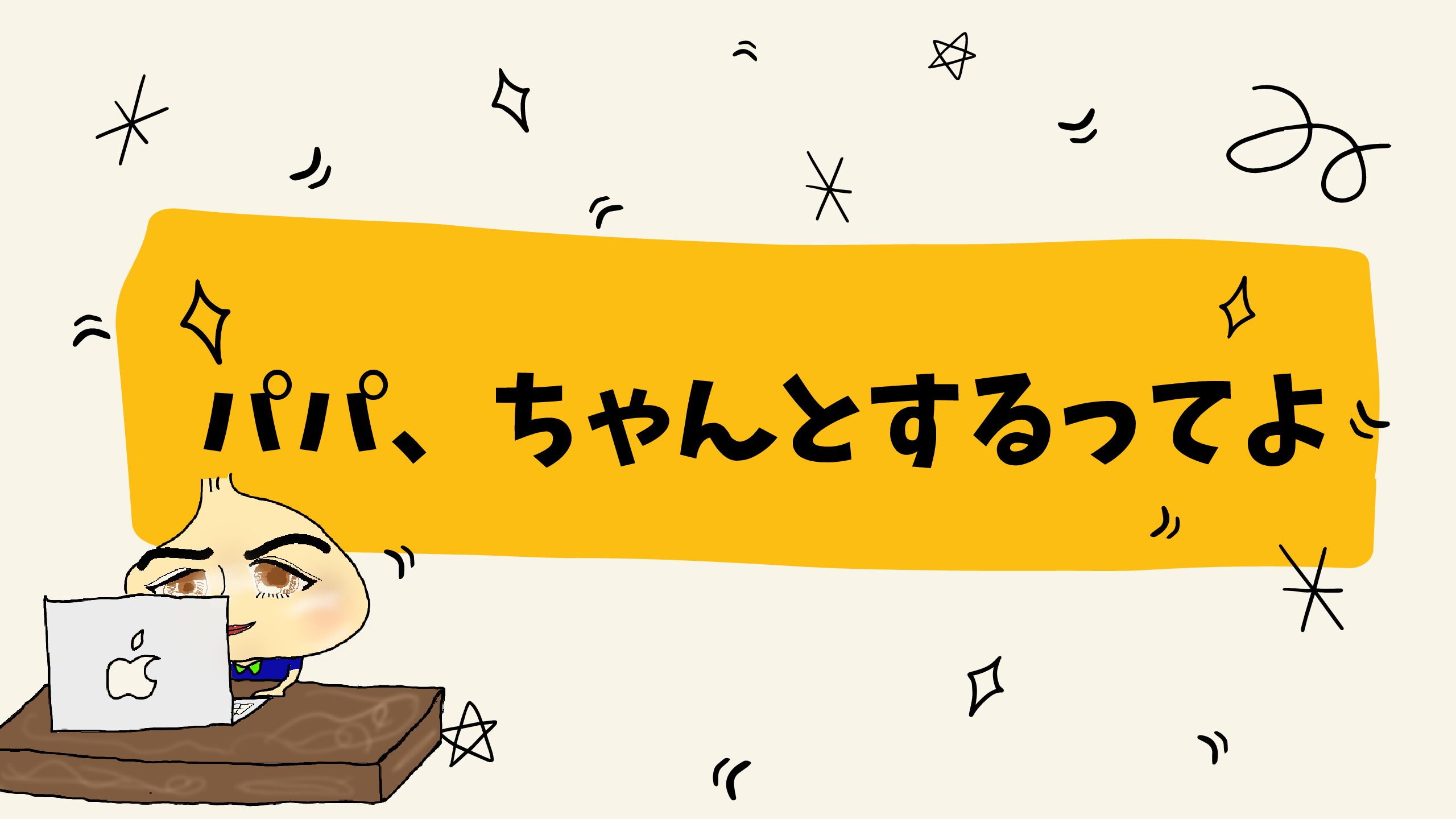


コメント