こんにちは。よよパパです。
教師のみなさん、今僕たちのブラック労働環境が叫ばれていますね。
どうですか?労働時間。働きすぎてませんか?

教師の仕事って「ここまで」っていうのがある意味なくて、「生徒の為に」でどこまででも働けちゃうんだよなぁ…

そうだね。僕も働き始めは1日13時間とか平気で働いて30連勤とかしてたなぁ…
生徒のために時間をかけて授業準備をして、部活動を見て、その他の業務もたくさんこなすことは大切です。
しかし早く帰って、大切な家族と過ごしたり、自分の趣味に没頭したり、自分の勉強に励んで、成長し続けていく教師でありたいものです。
その為には幅広く、量の多い仕事を効率よく捌かなければいけません。
この記事では3年担任、学年主任、バスケ部主顧問、生徒指導担当を務めながら月の残業時間20時間内に納めたよよパパが残業しすぎない為の仕事術を書いています。
1. 生徒との関係作りを第一に

残業の中で1番イレギュラー、そう、生徒指導。
突発的に起こり、事の大きさによっては生徒を残したり、
保護者を呼ばなければいけなかったり…。
保護者もすぐに来てくれるわけではないのでそれを待って夜遅くまで…。
学年の教師はそれを待って道連れに…。
残業の1番の敵は生徒指導です。
生徒指導を「起こってから」する生徒指導から、「起こる前」にする生徒指導に変えるのです。
普段から「いらんことすんなよ」って言うやつじゃありませんよ。
生徒とたくさん関わって、話して、いい関係を築くということです。
そうすればもし何か生徒がやらかしてしまっても話が入りやすいし、「次」が起こりにくいからです。
僕は休み時間はもちろん、空き時間も、昼休みも教室や廊下にいるようにしています。
それは「監視」ではなく、生徒と学校生活を「楽しむ」為に。
基本的に教師の仕事は生徒と関わることが9割です。
その生徒と悪い関係や希薄な関係では仕事がうまく、楽しくいくはずがありません。
仕事を円滑に進めるには生徒との関係作りが第一なのです。
2. できる仕事は教室で
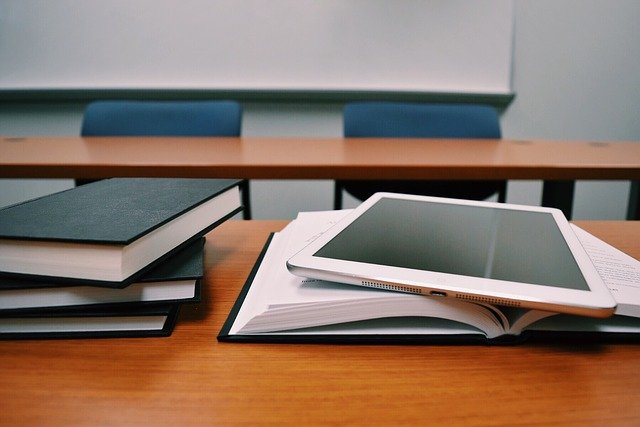
「デスクワークをする場所=職員室」では必ずしもありません。
職員室は仕事の手を止める要素がたくさん詰まった部屋です。
同僚からの世間話(不必要だとは思いませんが)、電話、突然ふってくる仕事などなど…。
なので僕は仕事はなるべく教室でするようにしています。(もちろん生徒に見られて困るものは職員室ですが)
教室でやる方が断然集中できます。
さらに子どもの他教科の授業中の様子も見れます。
たまに授業に参加したりしたら子どもは喜んでくれますしね。
また「先生何やってんのー?」と必ず聞いてくる子がいるので、
「一応おれってたくさん仕事あって頑張ってるんだぜ?」アピールにもちゃっかりなるわけです。
さらに生徒と一緒にいる時間を増やせるので単純に1にも書いた「生徒との関係作り」にも繋がってきます。
教室で仕事をするための1つのツールとして活躍してくれるのがiPadです。
僕は授業だけでなく、普段の校務もiPadで管理、実践してきました(もちろんパソコンでやることもありますが)。
学級通信作りやスケジュール管理、簡単な仕事などなど…。
詳しくはこちらの記事に書いていますので、参考にしてみてください。
3. 生徒ができそうなことは生徒にやってもらう
副担任と比べると担任ってやっぱりやる事多いですよね。
回収物のチェックや、懇談の日程調整、クラスの掲示物などなど…。
そんな担任業務、生徒に任せてしまうのはどうでしょう?
もちろん生徒にさせれない業務もありますが…
あるあるでは掲示物を手伝ってもらう。とかでしょうか。
他にはクラスの窓開け閉め、備品の整頓、机の整頓などなど…
まぁ担任がどれだけ担任業務をやらないかってのが仕事が早く終わる&生徒の自治力を高めるカギだと思ってます。
中学生になるとお手伝い頼んでも拒否られる事は往々にしてあるので子どもをノセル為のテクニックは心得ておかないとですね。
4. 部活動は自治力を高めさせる
中学、高校のノー残業の大きな壁、部活動。部活の活動時間自体はなかなかどうしようもなりませんが、部活の運営方法を変えることで負担はだいぶ軽減されます。
詳しくはこちらの記事に詳しく書いてますのでご覧ください。
5. まとめ
いかがでしたか。
その他にも他の著名な先生方が挙げている長期休みでのプリント等のまとめ刷りなどのアイデアもありますがここでは割愛させてもらいました。
僕が一番No残業に大切だと思うのはやはり生徒との関係性だと思っています。
そしてその関係性は残業だけでなく、授業、クラス、そしてその他の場面でも大きく影響してきます。
「だから」生徒との関係性を大事にするというわけではないです。
生徒と楽しくいい関係で仕事ができたら教師として最高に幸せですよね。
それが結果、自分の働き方にも還って来ると思ってます。
読んでいただきありがとうございました。
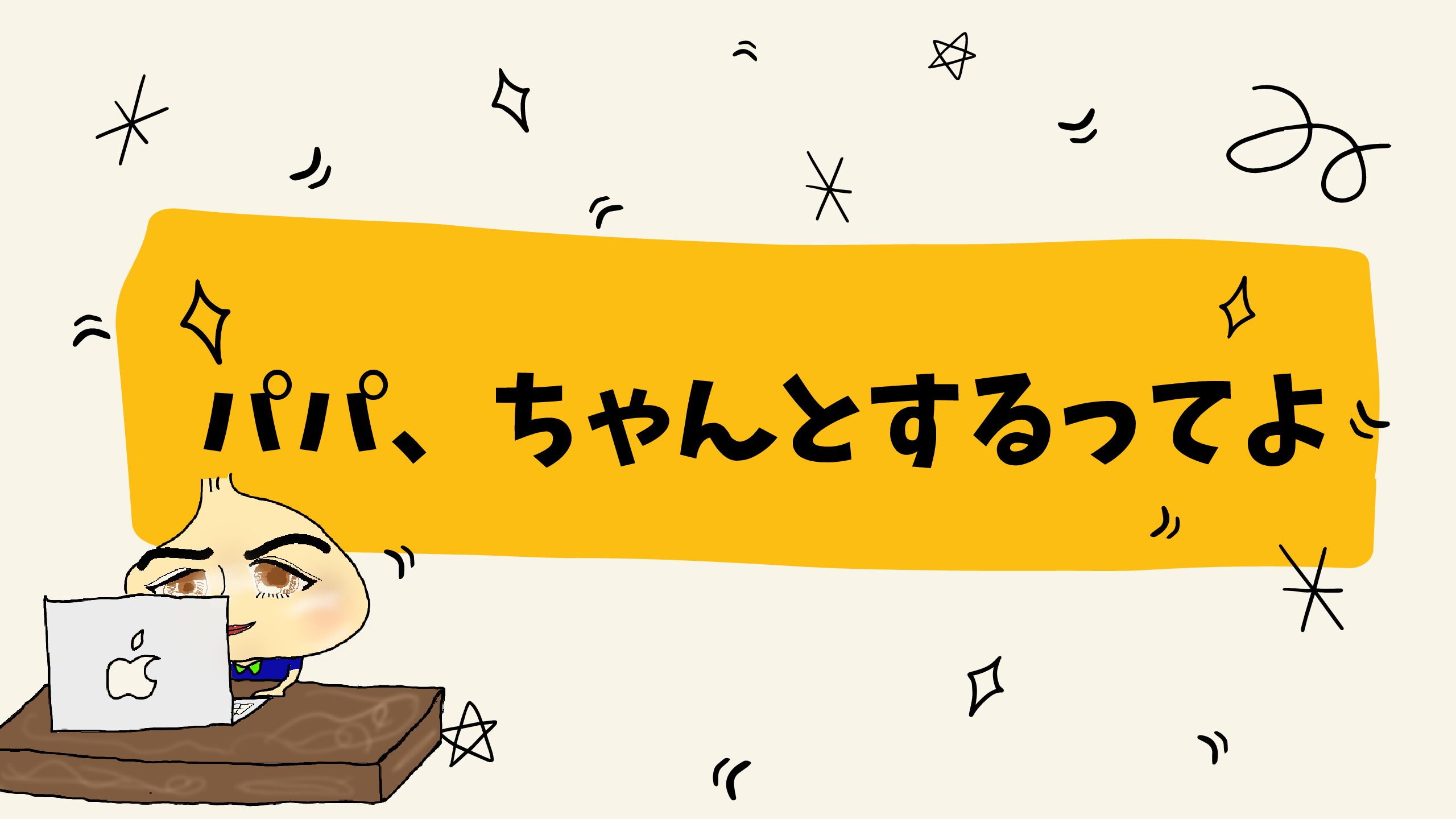
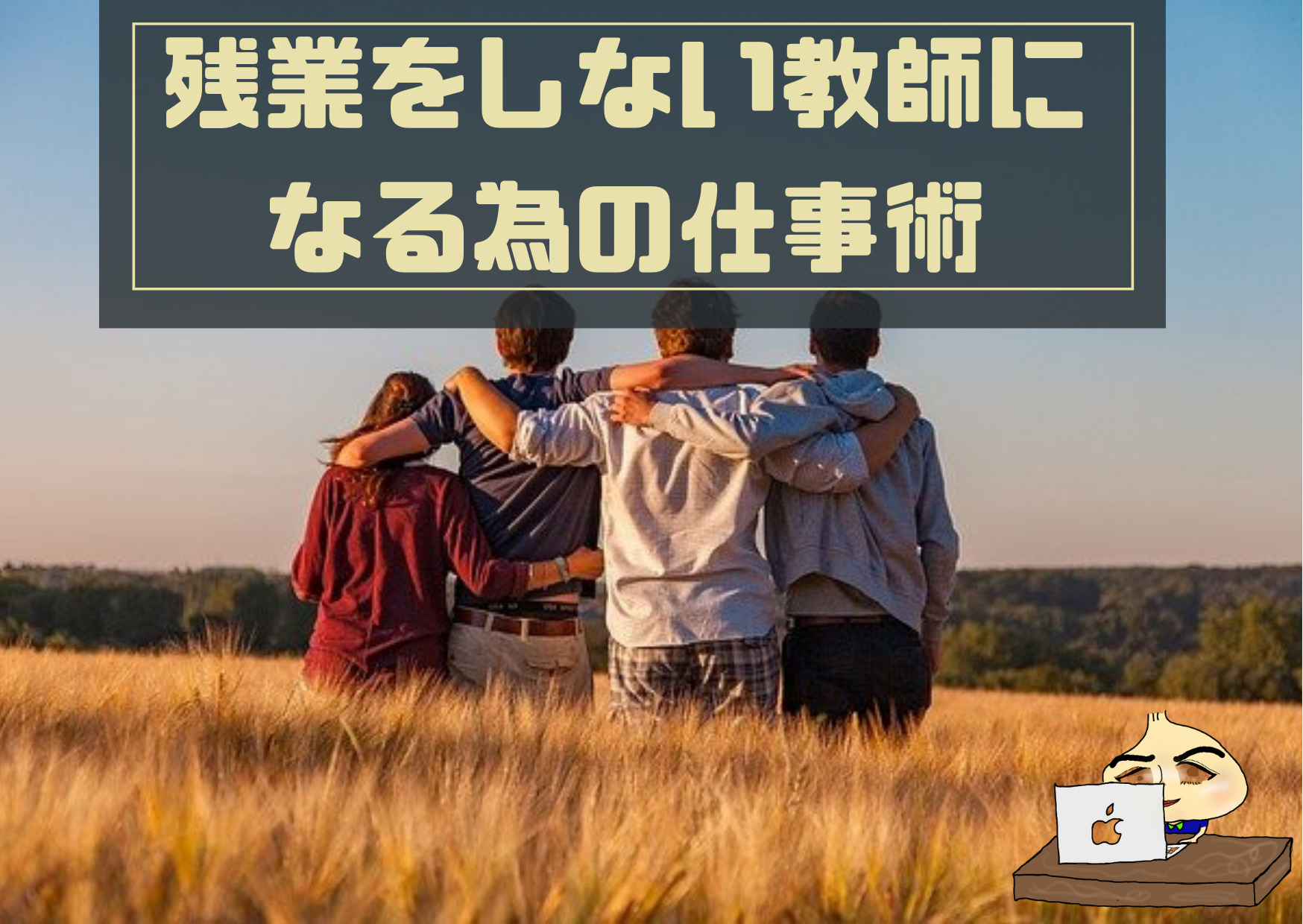





コメント